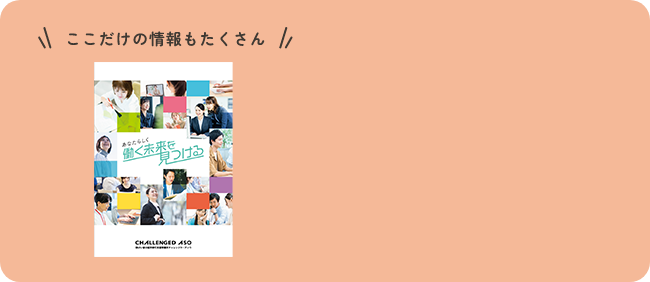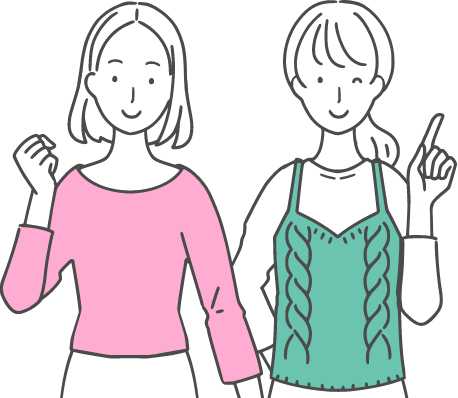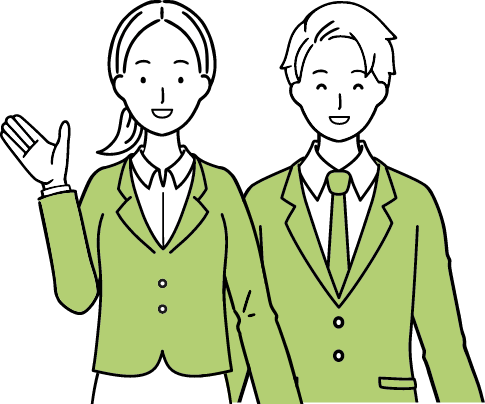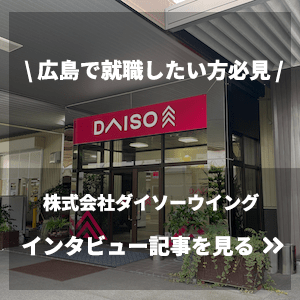環境の変化や強いストレスによって心身のバランスが崩れ、働くことが難しくなる「適応障害」は、誰にでも起こり得る病気です。
大切なのは早めに立ち止まり、適切な手順で休み、回復し、復職するときには安心して働ける土台をつくること。
本記事では、適応障害の基礎理解から、休職が必要かどうかの判断軸、会社への伝え方と手続き、休職中の収入を支える傷病手当金の仕組みまでを、順を追って丁寧に解説します。
さらに休職中の過ごし方や復職時のポイントなどもご紹介します。
チャレンジド・アソウでは、すべての事業所で休職中の方の復職をサポートしています。
リワーク支援に特化した事業所もあり、詳しくは下記特設サイトをご覧ください。
適応障害とは?
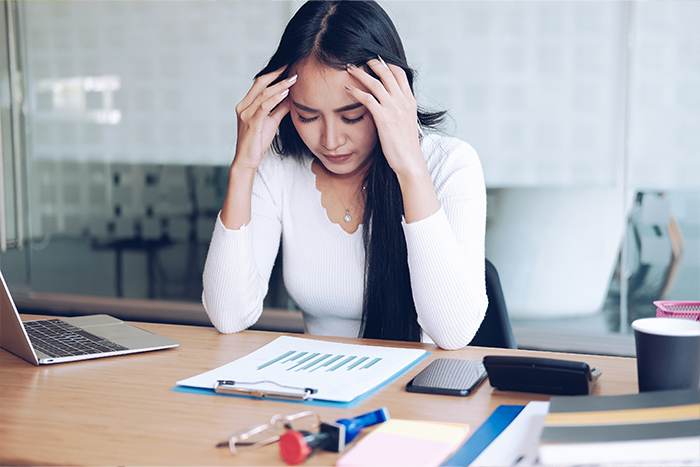
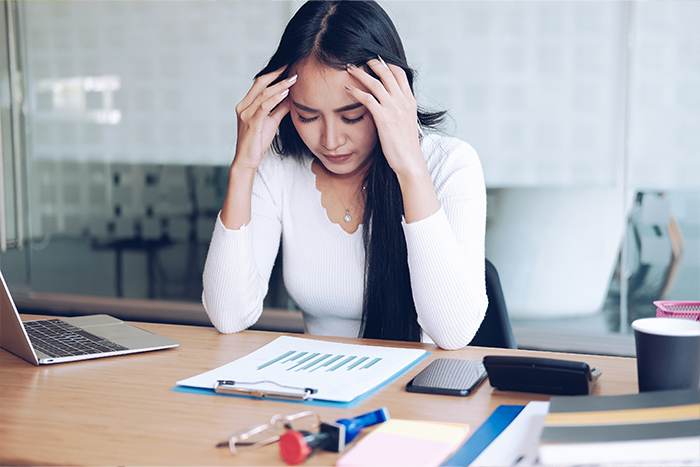
適応障害の症状と要因
「仕事がうまくいかない」「職場の人間関係に疲れた」「環境の変化に対応しきれない」
このようなことから心身のバランスを崩し、たとえば眠れない・やる気が出ない・イライラが止まらないといった症状が続くとき、「適応障害」が背景にある可能性があります。
適応障害とは、環境の変化(たとえば仕事内容や部署異動、昇進、人間関係など)やストレスとなる出来事(仕事・家庭など)をきっかけに、精神的・身体的な不調が現れ、社会生活に支障が出る状態を指します。
症状としてはまず、睡眠トラブル(眠れない、夜中に目覚める、早朝に目覚めてしまう)、朝起きるのがつらい、慢性的な疲労感、気分の落ち込み・イライラ・意欲低下、不安や焦燥感など心の症状が多く見られます。
これは初期段階でも起こりうるものです。
さらに症状が進むと、「遅刻・早退が増える」「仕事のミスが増える」「同僚や上司とのコミュニケーションが難しくなる」「出勤・勤務が続かない」といった支障が出てくることがあります。
これはいわば中等症~重症域に近づいたサインといえ、実際に休職や通院を要するケースも少なくありません。
要因としては大きく2つに分けて考えられます。
ひとつは「ストレッサーとのミスマッチ」です。
たとえば仕事内容や役割が変わった、上司や同僚との関係性が悪化した、新しい環境に馴染めない、家庭やプライベートの変化が大きかったなど。
もうひとつは「個人側の適応力や心身の状態」です。
もともとストレスに弱い、睡眠や休息が十分でない、加えて過去にメンタル不調の経験がある、プライベートで何か抱えている、などといった背景があると、同じストレスであっても不調に至る可能性が高くなります。
適応障害はストレス源を取り除いたり軽くすることで比較的早期に改善するケースもありますが、無理を重ねたり、適切な休息・治療を受けずに放置すると、長期化・再発化のリスクもあります。
適応障害の診断基準
適応障害の診断は心療内科や精神科などで行われ、医師が症状・背景・機能障害の程度を総合的に評価します。
具体的には「環境の変化やストレスフルな出来事に対して、通常予想される範囲を超える反応が出ていて」「その結果、日常生活や職場・学校での適応が著しく困難になっており」「精神的・身体的な症状が6か月以内に出現している」などがひとつの目安とされます。
また適応障害の診断には、うつ病や双極性障害、統合失調症など別の明確な精神疾患で説明できないことや、ストレス因(環境要因)が明確であること、そしてその症状と適応困難の因果関係が比較的明瞭であることが参照されます。
加えて、職場において「仕事ができない」「出勤が難しい」「勤務継続が難しい」などの実質的な適応障害の状態(就業不能あるいは著しい制限)があると、休職・診断書の根拠にもなりやすくなります。
診断書を受ける際には、「業務が遂行困難」「出勤・勤務が著しく制限される」と記載されていることが休職手続きにおいてポイントになります。
メンタルヘルスと適応障害の関連性
近年、職場におけるメンタルヘルス不調が増加傾向にあり、特に「環境変化・職場ストレス・パワハラ・長時間労働・人間関係の摩擦」などが背景にあるケースが目立ちます。
適応障害は、このような「ストレス負荷に対して短期間に出る障害反応」として、メンタルヘルスの中でも比較的早期に発見・介入しやすい部類に属します。
つまり、うつ病ほど長期化していないけれど、放っておくと深刻化しうる“中間領域”とも言えるのが適応障害です。
メンタルヘルスという観点から見ると、適応障害の回復には「ストレス源の明確化」「その負荷の軽減」「休息・治療による回復」が大切です。
実際に、多くの医療機関・産業医から「ストレッサー(職場含む)から距離を置く」「勤務形態・環境を見直す」「適切な休息・睡眠を取る」ことが重要という指摘があります。
そのため、早期に「自分は辛いかもしれない」と感じたら、無理せず医療機関を受診し、環境・勤務条件・負荷を見直すことが、休職・復職を含めた早期の改善・再発防止につながります。
休職の流れと手続き


休職の必要性とその判断基準
「もう限界かもしれない」「出勤するのがつらい」「仕事に集中できない・ミスが増えている」という状態が続いたとき、休職することも選択肢に入れましょう。
実務上、次のような状況が休職判断の目安となります。
- 毎日眠れず体が動かない
- 朝起きられず遅刻・早退が頻発
- 仕事の手が止まる
- 同僚や上司とのコミュニケーションが取れない
- 勤務継続によって症状が悪化している(不眠→体調不良→さらに休みが必要に)
こうした状況では、仕事を続けながら徐々に改善を目指すよりも、「一旦休んで治療・回復を優先する」という選択肢が現実的です。
「休職が必要な判断基準」として、医師による「仕事ができる状態ではない」という診断が挙げられています。
また休職制度自体は法律で必ず定められているわけではなく、多くの企業では「就業規則」や「休職規程」で休職期間・給与の支払い有無・復職条件が決められています。
つまり休職できるかどうかは、勤務先の制度内容や相談のしやすさ、上司・人事部門の理解と協力状況にも左右されます。
休職したいと思った時には、まず医療機関受診→診断書取得→上司・人事相談という流れを抑えることが重要です。
休職=“逃げ”ではなく、「治療・回復を目的とした適切なプロセス」として捉えましょう。
休職の手続きと必要書類
休職を決めたら、一般的に以下のステップをたどります。
まず医療機関(心療内科・精神科等)を受診し、診断書を取得しましょう。
医師には現在の症状と「勤務が困難」という旨を伝え、診断書に「労務不能」「療養・通院が必要」といった記載を得ることがポイントです。
次に会社に対して、上司・人事担当者に「休職の希望」「診断書を提出したい」という旨を伝えます。
この段階で、会社の就業規則・休職制度・休職中の給与・手当・復職プロセス等を事前に確認しておくことがおすすめです。
特に「休職期間」「復職時の条件」「給与の支払い有無/休業手当の有無」「引き継ぎ/業務整理」などを確認しておくと安心と言えます。
書類としては、主に次のようなものが必要になるケースがあります
- 医師の診断書(「就業困難」「療養中」などの記載)
- 休職申請書(勤務先の所定書式)
- 保険・手当申請用書類(後述の傷病手当金など)
休職中の給料と傷病手当金の支給
休職をしたとき、多くの人が気になるのが「収入がどうなるか」です。
まず基本的には「休職中だからといって会社が必ず給与を支払わなければならない」という法律上の義務はなく、休職制度自体も法定義務ではありません。
つまり、企業の就業規則・休職規程により「給与なし」「一部支給」など扱いが分かれています。
そこで利用したいのが公的な生活保障制度があります。
代表的なものに「傷病手当金」(健康保険からの給付)があります。
たとえば適応障害による休職でも利用できるケースが多々あります。
具体的には、次のようなポイントがあります。
- 傷病手当金の支給には「療養のため働くことができない状態」「連続する3日間を含み4日以上休んでいる」「休業期間中に給与の支払いがないこと(または少ないこと)」などの条件があります。
- 支給額は、標準報酬日額(直近12か月の給与等から算出)÷30日 × 2/3 が目安。
- 支給期間の上限は、開始日から最長で1年6か月です。
休職中に給与が一部出ている場合でも、給与額が傷病手当金の目安額を下回ると、その差額分が支給されるケースがあります。逆に給与が十分出ていれば、傷病手当金は支給されません。
休職前に「休職中の給与支払いはどうなるか」「会社に休職規程があるか」「健康保険組合に傷病手当金の対象となるか」などを確認しておくことが非常に重要です。
休職期間とその過ごし方


平均的な休職期間とその影響
実際に適応障害で休職する場合、どのくらいの期間が一般的なのでしょうか。
調査によると、メンタル不調(適応障害を含む)での平均的な休職期間は「約107日(約3.5か月)」というデータがあります。
ただし、これはあくまで平均値であり、症状の程度・職場環境・治療開始までのタイミング・支援体制などによって前後します。
軽度であれば1か月程度、中等度であれば3〜6か月、重度または再発後であれば1年以上の期間が必要になることもあります。
企業によっては休職可能な期間を「3か月〜1年半程度」と定めているケースもあり、その満了時に「復職」あるいは「退職・自然解雇」の判断に至る場合もあります。
休職期間が短すぎると、症状が改善しないまま復職して再発・症状悪化につながるリスクがあります。
一方、休職期間が長期化すると職場との関係性・業務習熟度・自信・社会的つながりが希薄になることで「復職後の不安」「自己効力感の低下」「再就労時のハードル増」などの影響が生じる可能性があります。
そのため休職期間を決める際には「治療・回復」「環境調整」「復職準備」の3つをバランスよく検討することが重要です。
チャレンジド・アソウでは、休職中の方の職場復帰や転職をサポートしています。
詳しくは下記をご覧いただけますと幸いです。
休職中の過ごし方とアクティビティ
休職中は、ただ「休む」だけでなく、治療・回復・今後の働き方を見据えた過ごし方が鍵となります。
具体的には、まず「心と体の休養」が最優先です。
眠れない、体がだるい、頭が回らないといった状態であれば、無理に起きて活動を増やすよりも治療に専念することが大切です。
次に「少しずつ生活を戻すリハビリ期」を意識しましょう。
たとえば軽い家事・散歩・読書・通院・趣味など、できる範囲で心地よい時間を過ごしながら、「起きている時間を増やす」「簡単なルーティンを作る」「起床時間を徐々に整える」といった活動を少しずつ行うことが望まれます。
適応障害は「ストレッサーから距離を置く」「環境を見直す」「焦らず段階的に戻す」ことが改善に向けて有効とされています。
また、完全に休んでしまうと「仕事から離れている自分」「社会から取り残されている」という感覚や罪悪感を抱きやすいので、「自分にとって心地よいスケジュール」を設けておくのがおすすめです。
たとえば「毎日同じ時間に起きる」「午前中は軽い散歩」「午後は趣味や通院」「夜はゆったり読書」など、無理のない範囲で“活動のリズム”を作ることが、復職に向けた土台づくりにもなります。
また治療(服薬・通院・カウンセリング)については必ず継続し、主治医の指示を守るようにしましょう。
罪悪感を軽減する方法
休職すると、「自分だけ休んでしまって申し訳ない」「復帰できるのだろうか」「キャリアが停滞したらどうしよう」というような罪悪感や焦り、将来への不安を感じる方が少なくありません。
しかし適応障害で休職することは決して“甘え”ではなく、むしろ「治療・回復・再発防止」のための適切な選択です。
そうした思いを和らげるために、次のような方法を実践してみましょう。
まず、休職中の自分を「回復に向けて努力している人」として自身を認めることです。
休養・治療・環境調整に時間を使うことは、将来的に働き続けるための投資でもあります。
次に、スマホや手帳に「今日やったこと」を記録しておくことです。
たとえば「通院に行った」「散歩30分した」「規則正しい起床」など、小さな成果を書き留めておくと、「休んでいるだけ」という感覚ではなく「回復に向けて進んでいる」と実感できます。
また家族・友人・信頼できる人に「今は回復のための大事な時期だから」と説明しておくことも有効です。理解を得ることで、精神的な負荷が軽くなります。
さらに、復職に向けて私たちのようなリワークセンターに通うことで、「少しずつできることを増やす」「復職後の自分をイメージする」「職場復帰で大丈夫なように準備している」と思え、焦り・罪悪感の軽減に繋がります。
チャレンジド・アソウでは、具体的に下記のリワークプログラムを実施しています。
- 最初は週1日など、自分のペースで利用開始
- あなただけの支援プランを作成し、自分に合ったプログラムが受けられる
- たくさん話を聞いてもらえるカウンセリング
- 「CCフィットネス」で体力&生活リズムの改善
- eラーニングで休職中にスキルアップ
- セルフケアとアラートサインの仕方を学び、ストレスを溜め込まない
- あなたに合った時期や部署、仕事内容で復職できるように企業と調整(職場復帰支援プランの作成、復職の時期や休職期間の延長、復職する部署や仕事内容・業務量の調整、最初は短時間勤務やテレワークからスタート、合理的配慮のレクチャー など)
- 再発・再休職しないように復職後も継続サポート
職場復帰に向けた準備


復職のための診断書の取得
休職期間を経て「そろそろ働けそうだ」という段階になったら、まず「復職可能な状態かどうか」を医師・産業医と相談することが重要です。
復職に際しては、職場によって「主治医または産業医の診断書」「勤務可能時間・勤務形態の意見書」「リハビリ出勤(時短勤務・徐々に勤務時間を増やす)制度の確認」などが求められます。
診断書には、「業務に復帰可能」「勤務時間を〇時間以内」「通院が必要だが業務に支障なし」などの記載があると、会社・産業医・本人間の合意が取りやすくなります。
特に休職期間が長かった場合、復職後の環境調整(業務軽減、人間関係フォロー、就業時間短縮など)がスムーズに行えるよう、診断書・意見書の内容を踏まえて職場側と調整することが望まれます。
私たちのような復職支援センターをご利用いただくと、この連携調整もスムーズに進めやすくなります。
なお、復職の直前に「ちゃんと働けるかな?」と不安になるのは自然なことであり、関係者と協力して「復職プラン」を作ることが、復職後の負荷軽減に繋がります。
職場復帰の流れとポイント
典型的な復職の流れとしては、以下のようなステップがあります。
まず本人・主治医・産業医・職場(人事・上司)・支援機関で、「復職可能・条件・リハビリ出勤の可否」などの協議がなされます。
次に「復職時期」「勤務時間・勤務形態」「業務内容の調整・配慮」「フォローアップ体制(面談・相談窓口)」「再発時の対応」などを決めた上で復職します。
ポイントとしては次の通りです。
まず、無理をせず「段階的に戻す」ことです。
急にフルタイム・フル負荷で戻ると、再び適応困難・再休職に至るリスクがあります。
次に、勤務開始後にも「定期的なフォロー面談」「業務量・勤務時間の見直し」「心身の状態確認」を継続することです。
復職前に「今後どのようなサポートがあるか」「役割・業務内容がどう変わるか」「人間関係・環境調整は済んでいるか」を確認しておくことが安心材料となります。
また、本人としても「自分の限界・ペースを知る」「調子が悪ければ早めに相談・勤務形態を変える」「定期的に休息を取る」「ストレスサインを見逃さない」などを心がけましょう。
復職=ゴールではなく、新たなスタートと捉え、「働き方を見直し、再発を防ぐ」という視点を持つことが重要です。
チャレンジド・アソウでは、そのためのサポートを行っております。
再発防止に向けたサポートプログラム
復職後、あるいは休職前後には再発防止を目的とした復職支援プログラムが有効です。
企業やリワーク支援機関などがその代表です。
たとえば勤務時間の段階的な増加(時短勤務→通常勤務)、業務内容の軽減・役割再設計、定期的な産業医相談・ストレスチェック、メンタル不調時の早期相談体制の整備などが挙げられます。
実際、休職からの復職プログラムを整備している企業では、復職後の離職率・再休職率が低くなっているという報告もあります。
本人として取り組めることもあります。
たとえば「自分にとってストレスとなる状況を整理(何が辛かったのか、何を変えたいのか)」「定期的に休息・カウンセリング・通院を継続」「勤務中・勤務後の疲労サイン・睡眠・食事・運動をモニタリング」「支援を求めやすい人・窓口をあらかじめ確認しておく」などです。
こうした準備が結果的に「長く働き続ける」ための基盤になります。
復職に向けての準備が不安な方は、まずはチャレンジド・アソウにご相談ください。
安心して復職できるように、丁寧にサポートします。
休職中のメンタルヘルス支援


主治医や産業医との連携
休職中・復職準備中は、医療機関(主治医・精神科・心療内科)と産業医・職場の担当者(人事・総務)との連携が極めて重要です。
まずは定期的な通院・治療(薬物療法・カウンセリング・認知行動療法など)を継続し、回復状況を主治医と共有しておくこと。さらに復職時に産業医・職場側と「勤務形態・時間・配慮事項」をすり合わせておくと、復職後のトラブルを防ぎやすくなります。
また「現在の心身の状態」「勤務可能な範囲」「復職プランの確認」「フォローアップの頻度」などを、それぞれで共有できていると、本人側・職場側双方にとって安心感が高まります。
ストレスチェックの活用法
近年、労働安全衛生法の改正により多くの企業で実施されている「ストレスチェック制度」は、休職・復職のプロセスにおいても大きな役割を果たします。
ストレスチェックを単なる義務として捉えるのではなく、「自分のストレス状態を可視化するツール」「復職後の指標」「環境調整を検討するきっかけ」として活用することが望ましいです。
たとえば休職前にストレスチェックの結果が出ていたなら、そのデータを産業医・職場と共有し「どの部分が要改善か」「勤務条件をどう調整すべきか」の議論材料にできます。
復職後も定期的なストレスチェックを受け、「負荷が増えていないか」「次の休職リスクがないか」をモニタリングすることが推奨されます。
さらに、自身でも「睡眠時間・休息時間・勤務外の活動量・気分変化」などを記録しておくことで、ストレスサインを早めに発見でき、産業医・主治医・上司に相談しやすくなります。
このようなストレスチェック+セルフモニタリングが「再発防止のアンテナ」となります。
休職を伝えるためのメール例文
休職を職場に伝えるのは、多くの場合、精神的にハードルが高く感じられます。
体調が優れない中、どのように切り出せばいいのか分からないという方も少なくありません。
以下では、あくまで一例として「休職の申し出メール」の書き方をご紹介します。
内容・文言は勤務先の雰囲気・上司との関係性・ご自身の状況に応じて適宜調整してください。
件名:休職のご相談(氏名)
○○部 ○○課 ○○(氏名)
お疲れさまです。○○部の○○です。
このたび、私事で誠に恐縮ですが、
体調不良により医師より療養が必要との診断を受けております。
現在、勤務を継続することで症状が悪化する可能性が高く、
医師と相談した結果、「一定期間の休職」をお願いしたいと考えております。
つきましては、診断書を準備出来次第、
正式に休職手続きのご相談をさせていただきたく存じます。
ご多忙のところお手数をおかけいたしますが、
ご調整のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
○○(氏名)
このように、休職の意図を明確に伝え、対話の機会を設けることが大切です。
また電話・面談・メールなど、自分の体調に応じて伝えやすい方法を選ぶこともポイントになります。
休職を延長したい場合の対応法


休職を開始したものの、「もう少し療養期間を延ばしたい」「復職できる見通しが立たない」という場合もあります。
その際には、次のような対応を検討してみましょう。
まず、主治医・産業医に「現状」「復職見込み」「延長の必要性」を相談し、診断書または意見書を改めて発行してもらいます。
企業側と「休職延長の希望」を申し出る際には、治療状況・通院頻度・勤務可能な範囲・復職プランの再見直しを含めて説明できるとスムーズです。
会社によっては、就業規則に「○か月まで休職可」「延長は別途審査」「休職期限を超えると退職」などの規定を設けている場合があります。
休職延長を考える場合には、自社の規程を確認するとともに、早めに人事・上司に相談しておくことが望まれます。
期限を超えて復職できない状態が続くと、「自然退職」「解雇」扱いとなる可能性があるため注意が必要です。
また、延長の間も「通院・治療」「生活リズム維持」「復職準備(例えば通勤路確認・勤務時間調整の検討)」といった活動を少しずつ行っておくことで、復職可能な状態に近づきやすくなります。
私たちチャレンジド・アソウでは、休職から職場復帰、その後の安定就労までトータルサポートしております。
詳しくは下記をご覧いただくか、資料請求または相談予約をお申し付けください。