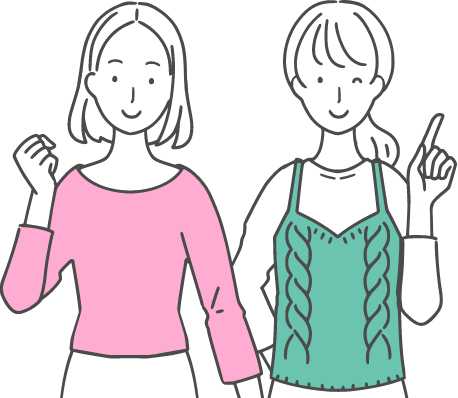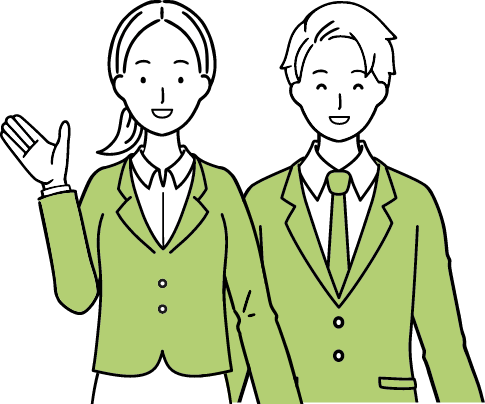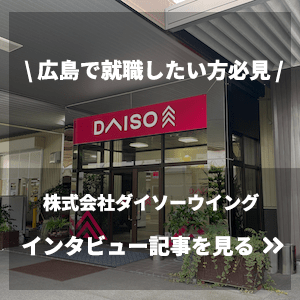障害のない人でも集団生活を送るうえでトラブルや苦情はつきものです。
就労移行支援事業所でも、トラブルや苦情に発展することがあり、全ての利用者が訓練に集中できるよう様々な対策等が講じられています。
そこで、今回は弊社に実際あった苦情を例に、就労移行支援事業所を運営する上で利用者からどんな苦情があるのかを紹介します。
そして、就労移行支援事業所では、利用者とどうやって向き合い、解決へと導いているのか、参考になれば幸いです。

チャレンジド・アソウ博多事業所
就労支援員 精神保健福祉士
監修:山本 慎也
15年に渡りテレマーケティング会社等にて
人材育成・マネジメント業務に従事。
行政コールセンターの構築にて福祉に
触れたことがきっかけとなり現職に至る。
利用する障害者からの苦情・トラブルと事業所の対応
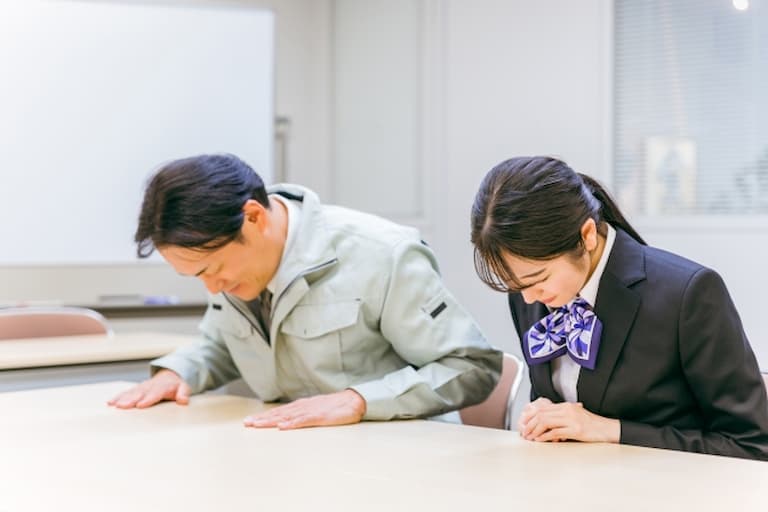
就労移行支援事業所の利用する障害者は、その特性や集団生活により、時にはトラブルや苦情に発展するケースがあります。就労移行支援の利用を検討中の方としては、どんなトラブルが起こり得るのかといったことは事前に把握しておきたいですよね。
そこで、ここでは就労移行支援事業所で起こりがちなトラブルや苦情の内容と弊社チャレンジド・アソウの対応を紹介していきます。まずは、よくあるトラブルを紹介してから実際にいただいた苦情の事例を紹介していきましょう。
就労移行支援事業所で起こるトラブル
就労移行支援事業所では、下記のようなトラブルが起こりがちです。
- 自分の希望する支援を受けられない
- 事業所のスタッフとの関係がうまくいかない
- 自分だけ不当に扱われている(いじめではないか?)
これらはあくまで利用者当人の感じ方をそのまま紹介させていただいております。中には、「勘違いがあった」「コミュニケーションが足りていなかった」といったこともあるので、事業所側でも積極的に調査を行い実態を把握します。
それでは、上記のようなトラブルが起こった際に就労移行支援事業所はどういった対応をとるのか、実際にいただいた苦情などをもとに紹介していきます。
利用者からの苦情とその対応
- 苦情内容:
早く就職したいのにトレーニングばかりで就職活動の支援をしてもらえない - 就労移行支援事業所側の対応:
就職活動を進めるよりもトレーニングが必要な理由を説明。現在の対策として、見学・体験にお越しいただいた段階で状況を伺い、就職までにかかる期間について説明し、納得いただいたうえで利用手続きに進んでいただく。
また、利用開始後も最低月1回の面談を行い、就職までのスケジュールを確認している。
- ご家族から子供の先行きが分からない。いつになったら就職できるのか
- ご家族・本人と面談し、現状を説明。このような苦情をご家族からいただく理由として、利用者本人がうまく説明できない、または話していないパターンがあるため、現在の対策として
①定期的に利用状況を利用者本人からご家族へ報告していただき、報告できたかどうかを都度利用者本人に確認する
②個別支援計画面談にご家族にも同席していただくか、電話で利用状況をご家族と共有するいずれかを行っている
- 社員に言われたこと・されたことで不快な思いをした
- そのときの状況を聞きとり、どのようなことが具体的に不快感を与えたのかを確認し、お詫びする。
利用者により不快に思う内容は異なるため、利用者によってどのような対応が不快感を与えるのかを社員間で共有する
- 他の利用者との扱いに差がある
(他の利用者には注意しないのに、自分にばかり注意する) - 当該利用者に対する社員の伝え方が不快感を与えた場合、お詫びする。
また、利用者によって課題やコミュニケーションの得手不得手が異なるため、伝えることや伝え方も変わることについて説明。(個人情報となるため、他の利用者の具体的な障害特性等については説明しない)
- 他の利用者に話しかけても無視される
- そのときの状況を聞きとり、今後の対応方法を検討する。利用者によって課題やコミュニケーションの得手不得手が異なるため、相手に悪意がなくても無視されたと感じる場面があることを説明。
(個人情報となるため、他の利用者の具体的な障害特性等については説明しない)必要に応じて、相手の利用者にも今後の対応や課題について説明する
- 他の利用者に好意を持たれて困っている
- そのときの状況を聞きとり、今後の対応方法を検討する。必要に応じて、相手の利用者にも今後の対応や課題について説明する。
トレーニング時間外での交友関係のトラブル防止のため、現在は利用者間での電話番号やメールアドレス等の連絡先を交換しないよう利用開始時に説明している。
障害の特性や人間関係の苦情が多い
上に挙げた就労移行支援事業所にある苦情の中には、障害の特性が原因であることも多いです。
また、利用者同士のトラブルによる苦情も多いです。
しかし、他の利用者の障害特性を伝えることは個人情報の観点から控え、話し合いや今後の対応策で納得してもらえるよう心がけています。
もし、苦情やトラブルに発展した場合は、当事者双方と面談等で事実確認を行い、解決へと導いていきます。
その他、就労移行支援事業所のスタッフに対する苦情があることも。スタッフに悪気がなくても利用者には嫌な思いを感じさせることがあった場合は誠意を持ってお詫びしています。
苦情の多くは就労移行支援事業所スタッフと利用者間の認識のズレや説明不足であることが多いので、相手を尊重しながら説明責任を果たし解決できるよう対応。
そして、利用者が就労移行支援に集中できるよう、職員間で利用者一人ひとりの性格や障害特性に応じた対応方法を共有していきます。
就労移行支援事業所のトラブル・苦情に関する相談窓口

最後に、就労移行支援を利用してトラブルが起きた場合にどうすればいいのか、その相談窓口などを紹介しておきます。
まずはスタッフや職員にありのままを伝えましょう
トラブルが起きた場合、まずはその苦情内容をスタッフ・職員に直接伝えましょう。利用者にトラブルが起こっていても、スタッフや職員が気づいていないということがよくあるからです。
この際、できるだけありのままご自身が感じたことを伝えるのがトラブル解決の鍵となります。苦情というのは伝える側も心苦しいところがあるものですが、伝えないと利用者様だけが不幸になってしまうので、できれば担当のスタッフに早いうちに相談するようにしましょう。
また、もし、スタッフや職員が苦情を取り合ってくれないという場合には、他の就労移行支援事業所を検討するのも一つの手です。その他、就労移行支援事業所以外にも苦情などの相談に乗ってくれるところがあります。それが地域の福祉相談窓口です。
市区町村の福祉相談窓口も相談可能
福祉相談窓口では、就労移行支援事業所をはじめとする福祉サービスの苦情や権利擁護、並びに成年後見制度の利用等の相談を受付けています。
例えば、東京都では福祉サービス利用相談窓口が設置されています。
なお、市区町村に苦情対応機関が設置されていない場合、都道府県に設置されている(社会福祉法人)〇〇県社会福祉協議会が、就労移行支援を含めた福祉サービスの苦情を解決するための第三者機関として「運営適正化委員会」を設置しています。
ここでも、就労移行支援事業所の利用に関する苦情について、面談や電話、メール等で相談することが可能です。
また、就労移行支援事業所の苦情を直接事業所に伝えられない場合にも、お住まい地域に設置されている運営適正化委員会に就労移行支援事業所の苦情を相談してみると良いでしょう。
まとめ
今回は就労移行支援事業所では利用者からどうな苦情が出ているか、そして、就労移行支援事業所側としてはどうやって対応しているかを実際にあったケースを用いて紹介してきました。
集団生活または共同作業を行ううえで、障害の有無に関係なくトラブルはつきものです。
しかし、就労移行支援事業所を利用する障害者全員が満足いくサービスが受けられるよう、研修や対応マニュアルなどを作成して苦情防止に日々努めています。
また、苦情が出た場合は、対応の振り帰りやフィードバックを行い、次回から同様の苦情が出ないよう対策を講じ組織間で共有。
さらに、保護者の方との連携もトラブルや苦情防止のうえで重要だと考え、面談や電話などを活用して就労移行支援の内容や進捗状況を共有していきます。
就労移行支援を成功するためには、職員・利用者・家族が三位一体となって連携し合うことが重要であると考えております。そして、当サイトを運営するチャレンジド・アソウでは、利用者さまとのコミュニケーションを大事にし、利用にあたってのトラブルなどにも親身に対応できる就労移行支援事業所です。
その他、業界トップクラスの就職率・定着率を誇るなど、就労移行支援をご検討中のあなたに自信を持っておすすめできる事業所ですので、ご興味のある方はぜひ次のチャレンジド・アソウについての紹介ページもご覧になってください。